気付けば6年生の第3回合不合判定テストが今週末と迫っています。個人の持ち偏差値というのは、6年下期に行われる4回模試の平均のことを指すので、いよいよ、という感じですかね。
2022年 第3回合不合判定テスト
基本情報
日時:
2022年9月11日(日)
時程:
| 午前 | 午後 | ||
|---|---|---|---|
| 集合時刻(入室完了) | 8:50 | 13:50 | |
| テスト開始時刻 | 9:05 | 14:05 | |
| 終了時刻 (予定) | 2教科 | 10:45 | 15:45 |
| 3教科 | 11:35 | 16:35 | |
| 4教科 | 12:10 | 17:10 | |
| 答案回収および解答解説配付後、解散 | |||
テスト時間・配点
| テスト時間 | 配点 | |
|---|---|---|
| 問題配布・諸注意 | 15分 | ー |
| 算数 | 50分 | 150点 |
| 国語 | 50分 | 150点 |
| トイレ休憩 | 15分 | ー |
| 理科 | 35分 | 100点 |
| 社会 | 35分 | 100点 |
その他、持ち物など詳細については受験要項をご確認ください。
中学校会場
以下の中学校が受験会場となっており、本番と近しい雰囲気での受験を経験することができます。
| 地域 | テスト会場 | 9/11午前 | 学校説明会 |
|---|---|---|---|
| 東京 | 足立学園中学校 | 男子のみ | × |
| 京華中学校 | 男子のみ | ○ | |
| 城北中学校 | 男子のみ | ○ | |
| 高輪中学校 | 男子のみ | ○ | |
| 獨協中学校 | 男子のみ | ○ | |
| 日本大学豊山中学校 | 男子のみ | ○ | |
| 吉祥女子中学校 | 女子のみ | ○(要予約) | |
| 共立女子中学校 | 女子のみ | ○ | |
| 香蘭女学校中等科 | 女子のみ | ○ | |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 女子のみ | ○ | |
| 女子聖学院中学校 | 女子のみ | × | |
| 山脇学園中学校 | 女子のみ | ○ | |
| 工学院大学附属中学校 | 男女 | ○ | |
| 成蹊中学校 | 男女 | ○(要予約) | |
| 成城学園中学校 | 男女 | ○(要予約) | |
| 東京都市大学等々力中学校 | 男女 | ○(要予約) | |
| 東京農大第一高等学校中等部 | 男女 | × | |
| 広尾学園中学校 | 男女 | ○ | |
| 文化学園大学杉並中学校 | 男女 | ○ | |
| 三田国際学園中学校 | 男女 | ○ | |
| 明治大学明治中学校 | 男女 | × | |
| 神奈川 | 日本女子大学附属中学校 | 女子のみ | ○ |
| 横浜雙葉中学校 | 女子のみ | × | |
| 関東学院中学校 | 男女 | ○(要予約) | |
| 千葉 | 東邦大学付属東邦中学校 | 男女 | ○ |
| 麗澤中学校 | 男女 | ○ | |
| 埼玉 | 大宮開成中学校 | 男女 | ○ |
| 栄東中学校 | 男女 | ○ |
四谷大塚サイトで合不合の情報が更新され、学校説明会の有無が公開されているので確認してみると良いと思います。予約が必要な学校があるので要チェックです。
特徴と注意点
受験前に確認したいこと
合不合判定テストそのものについては、第1回のときに記事にしたのでそちらを参考にしてください。
受験前に確認しておきたいことについては第2回のときにまとめました。内容は変わらないのでそちらを参考にしてください。
そこにも書きましたが、前年度(2021年)の合不合の問題が週テスト問題集に掲載されているので、これはぜひ入手してやっておきたいです。模試というのは塾がかなり力を入れて作成している最新の問題なので、今回の模試で点を取るためというよりも、良問にたくさん触れておくという問題演習の意味として重要だと個人的には考えています。予習シリーズにも合不合問題は掲載されていますが、こちらは古いので、時間がなくどちらか一方をというのであれば前年度問題をやるべきだと思います。
また、基本的にはこの第3回から第6回まで4回のテストを受ける方がほとんどだと思うので、事前の問題演習から模試終了後の解き直しまで、一連の流れを型にすることを意識しておくのが良いと思います。
昨年度(2021年)の情報
参考までに昨年度の情報を載せておきます。
総数 :15,508名
4教科 :14,422名
4教科男子: 7,776名
4教科女子: 6,646名
第2回の4教科受験者が14,987名だったので微減といった感じです。
算数(150点):69.5点(男子73.3/女子65.2)
国語(150点):76.7点(男子73.7/女子80.1)
理科(100点):46.5点(男子48.8/女子43.8)
社会(100点):51.5点(男子53.3/女子49.4)
4科(500点):245.6点(男子250.5/女子239.9)
平均点はまあ大体こんな辺りで標準的な感じはします。
さいごに
ここからは毎月の模試と過去問に追われ、全力で駆け抜けていく時期に入るかなと思います。
昨年の我が家は合不合とサピックスオープンの両方を受け、最新の問題に触れながら同学年内での立ち位置確認をしつつ、過去問を中心に学校との距離を測る作戦でいきました。おそらく色んな考え方があり色んなルートがあると思いますが、うまく模試を活用しながら乗り切ってもらえればと思います。
【追記】2022年結果
受験された方はおつかれさまでした。受験ドクターとコベツバによる講評と解説を記載しておきます。
受験ドクター講評
受験ドクターの解説速報を簡単に要約しますのでご参考まで。
全体講評・平均点予想
- 平均点は少し高め予想、男子80~85、女子85~90(もう少しいくかも)
- 今回読みづらかったり調子を狂わせて点数が下がる子供がいるかもしれない(大問1)
[1]
- 物語文は要約文が3つ入っている(=3箇所切り取られている)構成で、国語としては本来の姿でない。作問者の都合でツギハギになっているのは強引な誘導で、こう読んでほしいというものが強く出てしまい、読解力を測る試験としては疑問。
- (1)気持ちの説明としてふさわしいものを選ぶ、その後に語っている言葉から読み取る→四谷大塚では多いが、あまり入試問題としては一般的ではないと思う、選択肢問題として簡単
- (2)部分点取りやすい
- (4)記述としてはそれほど難しくない、誘導がかかっているので乗るべき
- (5) 易しい、本文の表現から読み取るのではなく流れから答えが見つかる(あまりいい問題ではないのでは)
- (6) 易しい
- (7) 標準的、表現に着目、文字に現されていない気持ちを読み取る問題
- (8) 本文と全く関係なく選べる
- (9) 身体表現を記号として捉える
- 今回の問題はテーマをこう読んでくださいと誘導がかかっているのでそこを外さなければ正解が取れる。(誘導をかけるのがうまい麻布は、問題を解きながら読みが深まっていく誘導の仕方をしていく教育的な問題の作り方をしていて、今回の問題とは似て非なるもの)
[2]
- 話し合いで決めていくことの利点
- 消極的理由と積極的理由からみんなで決めていくことがいいよねという論説文
- (1) 段落分けの問題はしばらくやっていないと間違えやすいので注意
- (2) 意外に間違えやすい、文章の前後の関係性を正しく追って把握できるか
- (3) 文脈から解ける問題
- (4-1) わかりやすかった、記述で出ることが多いのでできれば自分で書けるように、指示語は基本なので訓練して伸ばしてほしい
- (4-2) 文章中の言葉を使って問題は、本文に線を引いて線を見ながら書く、要素をきちんと全部入れること
- (5) イが紛らわしい、過不足ないのがウ
- (6) 「られる」は85行目に出ているので文章が読めていればわかりやすい問題
- (7) 簡単
- (8) 惑わされなければ簡単な抜き出し、何を高めて何を与えるかを考えていくとわかる
- (9) 正誤問題なら難しいが、選択問題なので比較的簡単
[3]
- 今回やっかいだったのが漢字・語句
- 今回答えと関係なかったものも、対義語があればおさえておいてほしい
- 漢字
- 特に難しかったのは9番、入試ではよく出るのでおさえておくといい
- 意外に忘れやすいのが「方便」
- 氷点下の「氷」を「標」とか書いていないか
全体講評・平均点予想
- 35分で大問6問はボリュームが多いので、知識で解ける部分の解答時間を短くしていき、計算や図を書くところに時間を割けるように
- 知識が4題でそれほど難しくなかったが、熱量やてこは慣れていないと大きく失点する
- 平均点予想は男女とも50~55点前後
[1]実験器具
- 多くの学校で出るのでしっかりおさえておきたい
- (3)目盛の読み取り問題は、指示がなくても1/10まで目分量で読むという点を知識として持っておく
- (5) 間違えやすいのはウとエの順番、どう考えれば正確に計れるのかをしっかりおさえる
- (5-2) いつでも答えられるように
[2]植物
- 知識が問われる問題
- 花びらの枚数だけでなく、合弁花/離弁花、肺種の数、自家受粉ができる/できない、などをおさえる
[3]熱量計算
- 難しかったのは問3-(3)
- (4)は知識問題、氷は水よりも2倍あたたまりやすい
[4]人体
- 大きく悩むところは少なかったので素早く解きたい
[5]来年度の入試を見据えた時事問題
- 多くの学校で出そうなのでしっかり復習してほしい
- 天体は作図することで解ける問題が多い、図を書く習慣を
[6]てこ
- 問1の棒の重さを間違えると全部間違えることになるちょっと怖い問題、あとに繋がる問題は慎重に
- 問5,6は難しい問題
全体講評・平均点予想
- 35分で5題なので時間は厳しい
- [1]と[5]はストレートな知識問題なのでまだ解きやすかった、[2]〜[4]がやや難しい
- 平均点予想は50点代前半
[1]公民:オーソドックスな知識問題
[2]コロナの時事問題:「インバウンド」「大阪万博」は聞かれる可能性あるのでおさえる
[3]融合問題:問7の監督官庁が違うのはもう一度確認しておく
[4]エネルギーや環境
- 問1:カーボンニュートラルの内容は記述でも書けるように
- 問5:オゾン層、マイクロプラスティックの原因と害、対応策をそれぞれ書けるように
- 問6-2:図表の読み取り、時間がなかった受験生も改めてやっておいてほしい
[5]歴史:大河ドラマ絡み、武士の時代
- 問8:鎌倉時代は女性でも領地を引き継いだという、イメージと違うものはおさえておく
全体講評・平均点予想
- 前回より解きやすいと感じた受験生が多かったのではないか
- ただ、苦手にする受験生が多いテーマがところどころにあったのでその対応により変わる
- [7][8][9]の(1)は落ち着いて見れば拾えるレベルの問題
- 平均点予想は男子は85点前後、女子は75~80点
[1]計算
[2]小問集合:解きやすい問題が並んだ
[3]倍数算:どの時点を問われているかを必ず確認するように
[4]N進法:問題を見たときにN進法の問題だと気付くように、今回は4進法、(2)は4進数のまま計算できる
[5]ダイヤグラム:ダイヤグラムとしては易しい部類の問題、距離一定・時間一定という速さと比の基本的な考え方がしっかり身についているかをこの問題で確認してほしい
[6]小問集合:今回は解きやすかった、(2)平方数が絡む数表、平方数を覚えているかどうかも重要
[7]立体図形:リード文をきちんと読めば解答方針が立つのでリード文に気を付けてほしい
[8]数の性質:具体的な例からどういう作業をしているかを読み取る、(1)素数だけを使って和が9になる組み合わせを書き出して掛け算をする
[9]点の移動:問題文を丁寧に読んで内容理解できれば(1)は拾えた、長方形を2等分する直線は対角線の交点を通るというのは確認しておく
(6年下期の合不合判定テストは)4回分で全範囲が揃う試験なので、4回受験ししっかり復習してほしい。
コベツバ講評
算数のみですがコベツバによる講評もあります。
- レベルAが6割、残りがレベルB
- 第2回とそれほど難易度は変わらない(第1回がやや難し目)
- レベルCがなく絶対的に解けない問題はなく、しっかりできる人とできない人の違いを生み出す内容
- 思考力問題が少なめ([8]と[7]-2くらい)
- [2]-(6)場合の数におけるCの利用は難関校で必要になる解き方なので知っておいてほしい
- [9]は技術に技術を重ねるような問題、渋谷渋谷が好きな感じ
詳しくは本家のサイトでも。
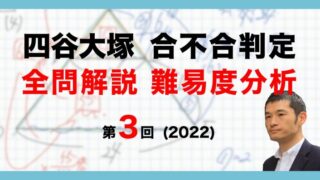
平均点
ネット情報から今回の平均点を載せておきます。
| 平均点 | 男子 | (昨年) | 女子 | (昨年) | 男女差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 算数(150点) | 72.5 | 73.3 | 64.5 | 65.2 | +8.0 |
| 国語(150点) | 81.2 | 73.7 | 90.3 | 80.1 | -9.1 |
| 理科(100点) | 45.6 | 48.8 | 41.4 | 43.8 | +4.2 |
| 社会(100点) | 51.6 | 53.3 | 48.5 | 49.4 | +3.1 |
| 4科(500点) | 252.4 | 250.5 | 246.6 | 239.9 | +5.8 |
受験者数:14297人(前年比 -125人)
平均点は前の年と大体同じくらいだったようです。受験者数はやや減という感じですね。
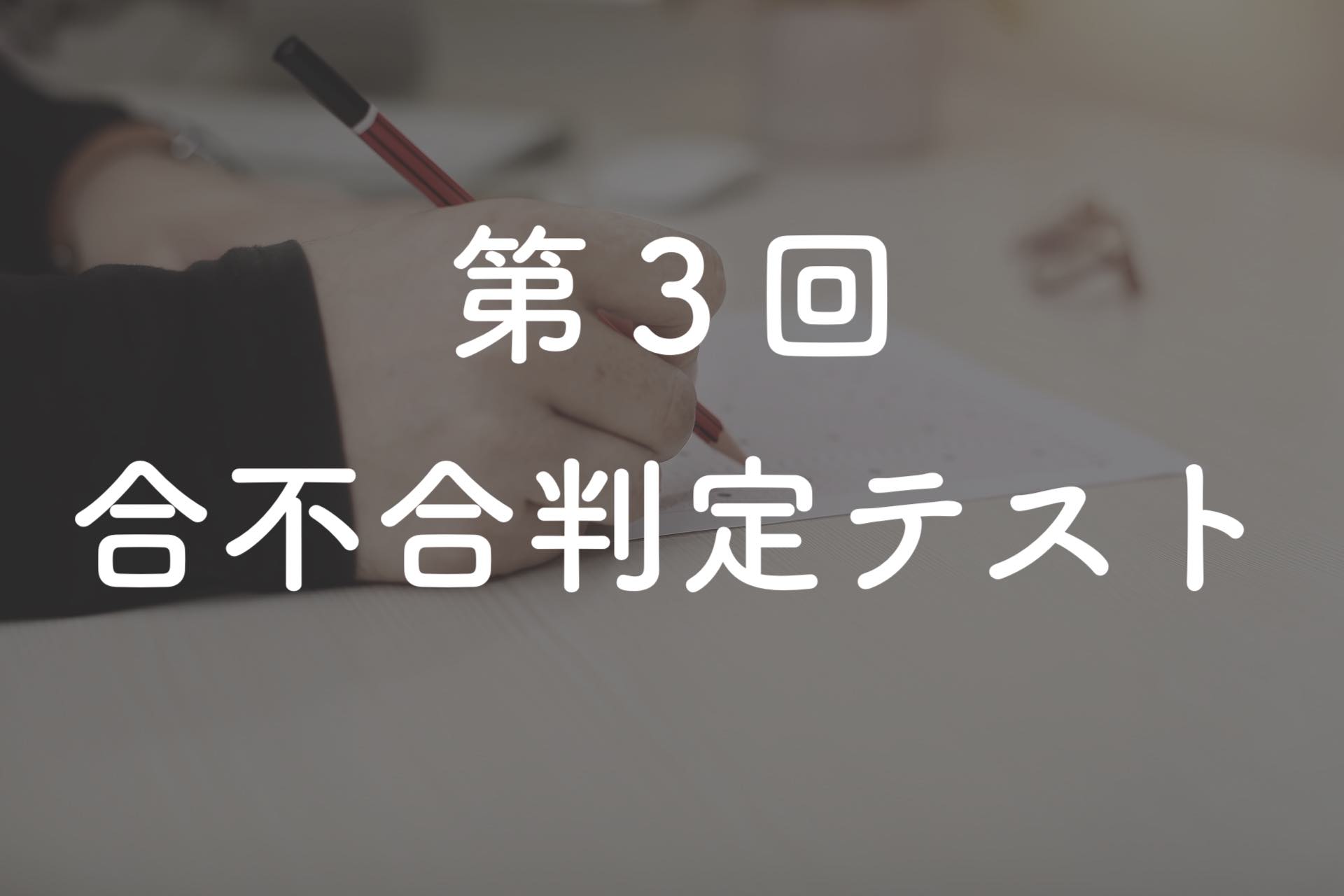
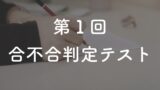
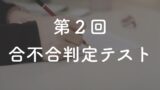














コメント