中学受験で語られる偏差値は、一般的に80%偏差値表が使われています。ただ、実際に入試を経験し理屈を理解してみると、50%偏差値表の方が重要じゃないかということに気付きました。その辺りをお伝えしたいと思います。
はじめに
中学受験の模試を受けると、配られる資料集には80%偏差値と50%偏差値という2種類の偏差値表が存在しています。サピックスではその名の通り80%偏差値と50%偏差値、四谷大塚(合不合判定テスト)だとAライン80偏差値とCライン50偏差値、日能研はR4とR3などと呼ばれているものです。
一般的に学校偏差値と言った場合は、80%偏差値表を使って話されることがほとんどです。例えば開成であれば、サピックスは68(S68と書かれたりします)、四谷大塚だと72(Y72)、日能研は72(N72)などとなっていて、これらがいわゆる学校の偏差値として語られますが、全て80%偏差値表の数字を使っています。志望校を考える際も、80%偏差値表を見ている人がほとんどだと思います。
では50%偏差値表って何でしょう?何のために存在しているのでしょうか?
塾では、第1志望は50%偏差値表から、抑え校は80%偏差値表から選ぶようにと言われることもあるらしいのですが、そこだけ聞いても意味がよくわからないというか、納得いかないですよね。その偏差値で半分が合格しているラインが50%偏差値だということで、これを、半分も受かっているのでチャンスがあると捉えるか、半分も落ちているので危ないと捉えるかでも全然印象が違いますよね。そもそも合格確率50%しかない学校を、他校の可能性を削ってまでなぜ受験しないといけないのか、塾の合格実績のために無謀なチャレンジをさせられているのでは、などと感じても不思議ではないと思います。
というか、息子の受験時、50%判定の意味に気付く前までの私がそう考えていました。
息子が6年の秋、合格力判定サピックスオープンを受けた後に公開されたサピックスの入試動向動画の中で、この50%判定の意味についての説明がされていました。それが、なるほどそういうことかと目から鱗が落ちる内容で、これによって偏差値に対する解像度が上がったというか、直前期は50%偏差値こそが見るべき指標だという考えに変わりました。そもそも模試でXX%判定とか言われても、漠然としていて不安だけが募るのが実際のところですが、50%判定の意味を理解すると具体的な数字が見えてきて精神的な安定感が全然違います。
ということで、合格判定の意味も含めて偏差値について解説してみます。
80%・50%偏差値とは
そもそも80%偏差値(80%判定)や50%偏差値(50%判定)って何でしょうか?ここはサピックスの受け売りですが、簡単に解説したいと思います。
これは、その偏差値の生徒が80%、つまり100人受けたら80人(50%なら50人)が合格しているという数字です。前年の模試と実際の入試結果のデータをもとに作成されています。
例えば80%偏差値が65で50%偏差値が60の学校であれば、偏差値65だった受験生の8割が合格していて(2割は不合格)、偏差値60だった受験生の5割が合格していた(5割は不合格)ということになります。合格者・不合格者とも基本は正規分布するので、イメージ図にするとこんな感じ。

あくまでわかりやすくするための概念図ですが、合格者と不合格者が綺麗に分布すればこんな感じになります。この場合、偏差値65の部分で合格者と不合格者の割合が大体8:2になって80%偏差値ラインが引かれ、偏差値60のところで線がクロスして5:5(同じ人数)になり50%偏差値ラインが引かれるということになります。
まずは基本として、80%偏差値と50%偏差値がこういうものというのをおさえておく必要があります。
50%ラインの意味
さてここからが本題です。
50%偏差値のライン(50%ラインと呼ぶことにします)を中心に見て、以下の2つの部分に注目します。
①50%ラインを超えていたが不合格になった人(オレンジで塗りつぶした部分)
②50%ラインを超えていないが合格になった人(ブルーで塗りつぶした部分)

この①と②がほぼ同じ面積になっているということは、①と②はほぼ同じ人数だということが言えます。つまり、②の人数と①の人数を入れ替えることができるということです。この②の人数を右側に移動して①と入れ替えてしまっても人数は変わらないということから、50%ラインで切ったときの右側の人数は、合格者の総数と同じであるということになります。(下の図)

実際の入試では当然、点数の高い方から合格者が決まっていくので、仮に今回の模試が入試本番だったと仮定すれば、50%ラインより上(図で右側)の人が合格者であったとみなすことができるという理屈になります。
個人の目線で言うと、もし今回の模試で50%ラインを超えていれば、今回が入試本番だったら合格点を超えていた(合格者の人数に入っていた)とみなすことができるという意味となります。50%判定ラインというのは合格ラインである、と言い換えてもいいかもしれません。
実際にはこんな綺麗な分布にはなっていないのですが、理屈上はこうであるというのがここでおさえておきたいところです。
そしてここまでわかると、50%判定なら十分勝負圏内と考えられ、なぜ第一志望に50%偏差値表を使うように言われているのかも理解できるのではないでしょうか。
実際の塾のデータを見てみる
本当に50%偏差値までを合格者と考えていいのか、実際のデータを見て検証してみます。公開されていないデータをここへ載せるわけにはいかないので個別にはご自身で確認していただければと思いますが、サピックスと四谷大塚のデータについて軽く触れておきます。
サピックス
サピックスでは、学校ごと過去の入試データがマイページから閲覧できます。サピックス生はもちろんですが、サピックスオープン受験生も模試の翌月までは見ることができました(つまり12月まで受け続ければ受験直前まで見られます)。
それぞれの学校を受験したサピックス生(サピックスオープン受験生も含む)について、合格・不合格の人数グラフを見ることができます。縦軸の数値(具体的な人数)までは出ていませんが、大まかな人数の分布と80%/50%/20%ラインが書かれています。受験者数が少ないと有意なデータにならないので、サピックスからの受験生が多い上位校中心にはなりますが、志望校のデータがあればぜひ見たいところです。
ここではサピックスのサイトにあるサンプルを引用します。

このように実際のデータは綺麗な放物線ではなくジグザグしています。偏差値2ごとに区切っているのと、1目盛ごとの人数もせいぜい数十人レベルなので、多少デコボコしているのはまあそんなものでしょう。ただ全体を俯瞰して見ると、上で見たような理論上の形から大きくは外れていないのが分かると思います。

ここで、上の理論通りに①と②の色付けをしてみるとこんな感じになります。①と②の面積に大きな違いはなく、入れ替え可能だというのがわかると思います。元々サピックスから聞いた理論なので当然かもしれませんが、データの裏付けも確認できました。
ちなみに受験者数が少ないと、途中にゼロ人が出たりしてもっとデコボコしています。その場合、50%判定ラインも微妙な感じですが、上の理論で50%ラインは付けているだろうなという感じはします。(むしろ偏差値を付けるのが大変そうです)
四谷大塚
四谷大塚はサピックスほど細かいデータを出してくれていませんが、四谷大塚の発行している中学入試案内という本にこのグラフが載っています(四谷大塚システムを受講していると配られるやつです)。サピックスよりさらに上位のほんの一部の学校しか載っていないのが残念ですが、一応見られます。
これで確認すると、サピックスに比べてだいぶデータが丸められている感じはしますが、大体下のようなグラフになっています。

ここでひとつ気付くのは、50%ラインが必ずしも曲線の交点ではなく、それよりやや下の偏差値に引かれていることが多いということです。この場合、50%判定の偏差値では合格率は50%より下回り、不合格者の方がやや多くなっているということになります。
ただ別の視点で見ると、上の図のように①と②の面積は大体同じになっていることが確認でき、逆にもし交点の部分(上の図では61くらい)に50%ラインを引いてしまうと②の面積が大きくなってしまう感じになります。
ここから推察できるのは、50%偏差値というのは、①と②の面積を同じにすることに重きを置いて作られているということです。つまり、合格確率50%であることよりも、その模試での合格ラインという意味の方が強いということが考えられます。
まあその辺りの真偽はさておき、受験生側としてはその模試・その母集団で合否を付けた場合、50%判定から上は合格だった、ということを理解しておけばいいかと思います。
50%偏差値を有効に使う
以上、50%判定・50%偏差値とはどういうものかについて解説しました。では、どう考え、どう使えばいいのでしょうか。
おそらく第一志望の学校を考えるとき、目標とする偏差値は80%偏差値になると思います。これは目標値なので特に問題ないというか、一般的に使われるのも80%偏差値なので、目指すべきもそっちになるでしょう。少なくとも6年生前半まではその方が良いと思います。
50%偏差値が真価を発揮するのは6年生後半〜直前期です。
ここで重要なのは、50%偏差値・50%判定の意味をきちんと理解することです。それぞれの模試において、50%偏差値=合格ラインだと定めれば自分で合否判定ができます。そして、今回の結果で合格ラインに達していたのか、どのくらい余裕があるのか、どれだけ足りないのかを具体的にイメージすることができます。
模試の結果情報でもXX%判定というのは出ますが、80%判定とか30%判定とか言われても漠然としていてピンときません。80%判定を取っても20%は落ちるので安心感はないし、50%判定でも半分は落ちるということで不安だし、20%や30%なんて絶望感満載でしょう。結局、どんな判定が出たところで不安が募るだけです。
そうではなく、合格ラインに対しての立ち位置がどうだったかを見ていくのです。
例えば、持ち偏差値(6年生後期の4回模試の平均偏差値)が60だったとして、志望校の50%偏差値も60だったとします。80%偏差値だと大体ここから+3〜5のことが多いので、偏差値63〜65の学校だと思って見てください。この場合、模試の結果資料では50%判定で返ってきますが、合格可能性は半分かあ、うーん微妙だな、程度の反応しかできませんね。で子供には「もっと頑張らないと」とか漠然としたことを言うだけで終わりだと思います。そして偏差値も足りていないし、親の方は色々考えて不安になっていきます。
ここで上の合否ラインの考え方を使います。例えば平均偏差値が60だったときに、4回模試のそれぞれの偏差値について3つのパターンを考えてみます。
- 58・59・61・62で平均が60だった場合:合格ラインの60を超えたのは4回中2回なので、確かに合格確率は50%になります
- 58・58・58・66で平均が60だった場合:合格ラインの60を超えたのは4回中1回なので、合格確率は25%になります
- 54・62・62・62で平均が60だった場合:合格ラインの60を超えたのは4回中3回なので、合格確率は75%になります
こんな感じになります。2のケースの子は、まともにこの学校を受ければやや厳しい結果になると見えますが、問題がハマればもっと上位の学校でも合格が取れる可能性があります。3のケースの子は大コケさえしなければ割と有望に見えます。1の子も、58・59の回をもう一度見直して、どの分野・どの問題を取れば60に到達できたのかを考えていけば、そこから本番までに強化すべきことも見えくるでしょう(これは全ての子に共通することでしょうが)。
もう一度言いますが、これは80%偏差値で63〜65の学校を想定した話です。偏差値60の子で考えているので格上挑戦に見えますが、決してそんなことはないと思えませんか。
併願校(安全校)を考える際も、80%偏差値で何となく決めてもやはり不安になるだけなので、合格ラインからどの程度余裕があるか、合格ラインを下回る可能性があるかという観点で見ていくと、気持ちの上でより堅実な受験に持っていくことができます。
実際の入試は問題が違うので、より重視すべきはもちろん過去問の方ですが、客観的な学力指標である模試の相関も高く、結果を情報としてしっかり活かしていけると良いでしょう。模試と過去問を有効に使って志望校の対策をしていくのが合格への道だと思います。
いずれにせよ、合格ラインを意識してそこに対する距離感を把握することが重要で、それができれば不安や焦りを増幅させずにもっと建設的な対応策を考えることもできます。直前期の親で最も大事なのは、勉強計画を立てることでも子供のケツを叩くことでもなく、冷静になることだと私は思います。自らの不安に駆られて取った行動は大抵ロクなものではないと思った方がいいでしょう。
偏差値の意味を理解することで、過度に悲観したり楽観したりすることなく、冷静に受験戦略を立てるための材料にしていっていただければと思っています。















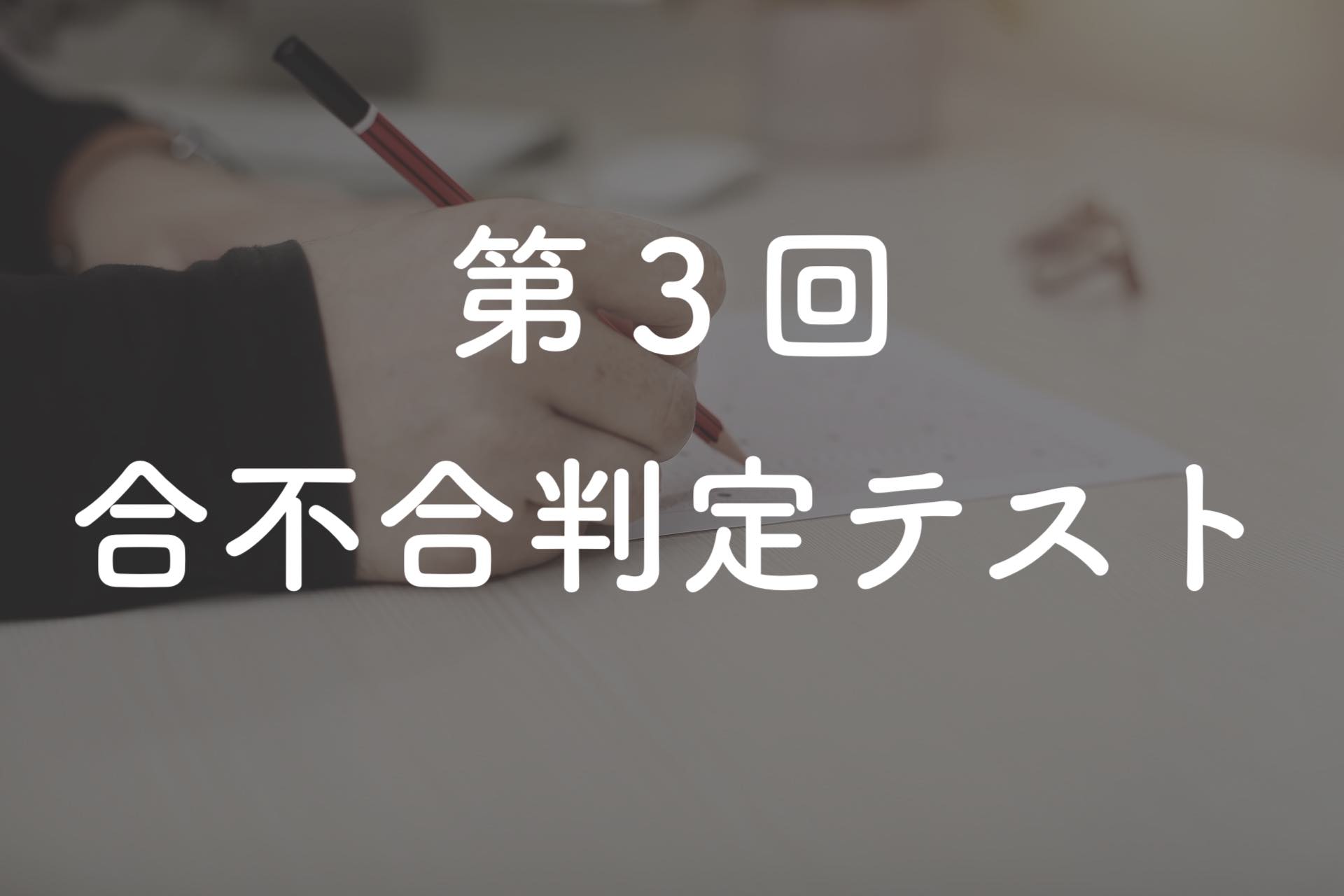
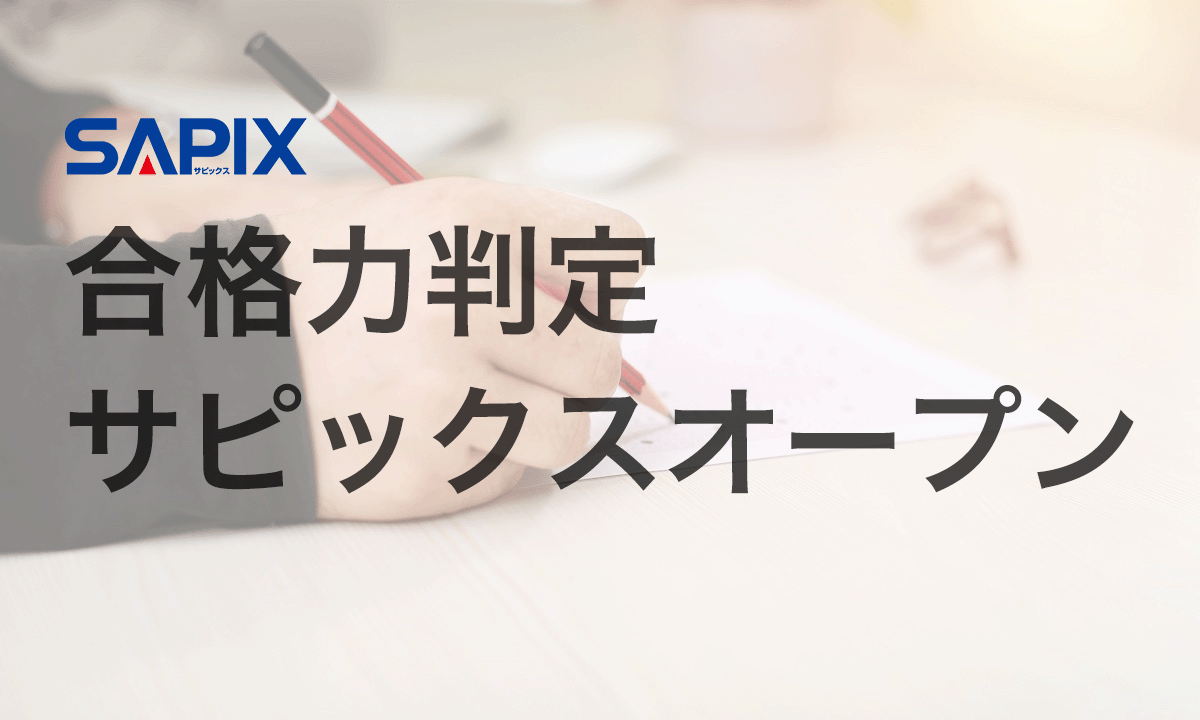
コメント