昨日6月12日は第2回志望校判定サピックスオープンでしたね。受験したみなさまおつかれさまでした。今回でA/B分かれた長丁場の6年生上期のサピックスオープンは終了、下期からは持ち偏差値の基準となる合格力判定サピックスオープンになります。
志望校判定サピックスオープンについてはこちらにまとめているのでご参照ください。
採点と集計の結果が公開されるのは木曜日だと思いますが、当日夜か翌日には採点前答案がマイページから閲覧できるので、それを見て早めに確認・解き直しをしておくのが良いでしょう。また、コベツバや受験ドクターで当日夜に速報解説もあるのでそれらも活用し、下期の模試に向けて、試験を受けた日の行動パターンを作っておくのが良いのではと思います。
我が家でも、受けた試験によって答案返却タイミングが異なるので若干パターンは異なりますが、サピックスオープンを受けたあとは、帰宅後の自由時間のあと、夜にコベツバと受験ドクターを見ながら解き直しというサイクルを作っていました。(配信が遅かった場合は翌日に回すこともありましたが)
塾で模試解説や解き直しまで丁寧にやってくれるケースは少ないと思うので、家庭教師などにお願いするのでなければ、こういった動画サービスを使って復習しておくのが良いのではないでしょうか。
また親御さんも一緒に、もしくは事前に見て、問題の難易度や傾向を把握しておくことも重要なことかと思います。成績表の数字だけでは、今回のテスト結果をどう評価すべきか冷静な判断は難しいと思いますし、どこまで解き直しをするべきかの指針もあった方がよいと思うので。
ここから、それぞれの動画解説のまとめをざっと書いておきます。
2022年 第2回志望校判定サピックスオープン
コベツバの解説(算数)
A問題
- レベルAが7割、残りがレベルBで通常通りの難易度
- 大問2で典型題ではないレベルBが入ってきたため難しく感じた人もいたのではないか
- 大問5が読解・整理で若干思考力要素の入った問題
- ポイントが明確な問題が多いので、気付かなかったものがあればしっかり復習してほしい
B問題
- レベルAが4割、レベルBが5割、残り(1割)がレベルCという難易度の高い構成だが、今回はそれでも比較的得点しやすい方だったのではないか
- 大問2は規則を整理して調べ、(2)(3)は(1)を使い、(4)も(1)〜(3)を使うなど段階に誘導がかけられているので解きやすい
- 大問3は思考力というより技術系に近い、丁寧に調べていけば答えが出る
- 大問2、3をいかに堅く取れるかが重要
- 大問1はやっかいだが(2)まで何とかできればよし、ただ時間を使いすぎてしまう恐れあり
本家サイトにも難易度分析があります。
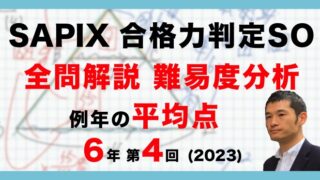
ちなみに有料ですが(無料お試しあり)全問動画解説もあります。Standbyという通常コースを取っていなくても、サピックスオープンや合不合などの模試だけ購入というのもできたはずです。
受験ドクターの解説
A問題
- 問題解説
- [2]-(3)のような問題を短時間で切っていけるか
- [2]-(4)仕事算の典型題だがひねった問題、イメージしやすい図を書く(動画中で解説あり)
- [2]-(5)苦戦した子が多そう、きちんと作図する判断ができたかがポイント(動画中で解説あり)
- [3]-(3)面積比が出せていない子は30度利用に要注意
- [4]良問、(2)は等差数列に持ち込む(動画中で解説あり)
- [5](2)までパパッと仕上げて、力があれば(3)に取り組む(動画中で解説あり)
- [6]直角三角形の相似、相似の中でも一番難易度は高い、(1)で誘導がかかっている
- 平均点予想は70後半(78)〜80点くらい
B問題
- 点数が読めないくらい難しかったので、解き直しは一旦置いておいてもよい(A問題を優先)
- 割合と比に関する出題がなく、難関校で求められる試行錯誤する力をみる問題
- [2]は(1)に時間をかけて書き出し正確に合わせることができるかがポイント、こういう問題は過去問に入ったときに部分点をもらえるようきれいに書き出して整理すること
- [3]場合分けを図示する、問題としては良問で普段のテキストにはないもの
- 今回は5年生までの知識で全て解ける問題
- 平均点予想は40点割るかもしれない、38〜42点(全体の点が悪ければ多少採点で調整が入るかも?)
A問題
- 標準的な問題で差がつく
- 平均点予想は90〜100の間
- 問題解説[1]
- 知識や語句問題が易しかった
- 問1〜問4は正解すべき問題
- 問3B(畏怖の念)は難しかったが、入試必須の言葉なので確実におさえてほしい
- 問5は確実に取ってほしいが、混同読みしてしまうお子さんは間違えやすい
- 問6は比喩表現の抜き出し、傍線を引かれていない比喩表現を見つけたらチェックしておく癖が付いていれば簡単に書けた
- 一読したときにマーキングして塊で捉えておくことで時間を短縮できる
- 問7は標準的な問題
- 問8は問5と同じく混同読みしてしまうと間違えやすい
- 問9〜問10はできるお子さんなら取れた問題
- 問11は一番難しかった、人物像問題は練習の機会が少ないのでしっかり復習しておきたい
- 問題解説[2]
- 対比で解く問題(開かれたこと、閉じられたこと)
- キーワードをそれぞれ対比のボックスに入れて読めば解きやすい
- 漢字は易しくはなかった
- 問2、問3はとても簡単なので全問正解を目指す
- 問4(1)(2)の抜き出し問題が、見当はつくが捉えにくい問題で難しかった
- 抜き出し問題は時間食い問題なので、戦略的に解く(2分で見つからなければ保留して先へ進むなど)
- 問4(3)は標準よりやや難しい問題なのでぜひ正解してほしい
- 問5は具体例の意味問題としては難しくない
- 問7は引っかけが多く間違えやすい
- 問8も難しかったが問7よりは易しい
B問題
- 小学生にはとても難しかったのではないか(カタルシスがないため)
- 物語文の一般的な型は、成長や葛藤、困難を乗り越えて何らかのカタルシスを得るというものだが、そこからわざと逸脱したものを出し本当に本文を読めているかを確かめるのがこの問題(サピックスでは年に1〜2度出し、この場合は大抵平均点が低くなる)
- 問8は26点と大きいが書けない子が多かったのではないか
- 多くの生徒が取れたであろう問題は前半(問1〜問4)、キーワードが抑えられていればOK
- “きんちゃく袋作りが逃避になっている”ということが理解できれば問5、問6、問8とも取れるが、非常に難しい問題
- 平均点予想は、採点が甘ければ60点、厳しければ50点を切ることもありえる
- 復習するときは、今手が付けられない問題は深追いせず、新しい問題に対して解き方・解法をチャレンジしていく方がよい
A問題
- 短い時間(20分)の中で大問4つをテキパキ解いていくことが必要
- [1]生物:筋肉と骨について、人体と鳥から出題
- [2]化学:気体の性質、(1)をどれだけ早くできたかが後半の計算問題をクリアするカギ
- [3]地学:太陽の日の出・日の入り、(6)(7)に時間をかけたいが、類題を過去に解いていたかで時間の余裕がかわる
- [4]物理:光の直進の性質、そこまで難しくはないが、時間が短いのでここで取れなくても他で取れていればよし
- 難易度は難しくないが時間ロスができないので、それが点数につながってくるテスト
- 特に計算問題など時間がかかったものは作業をしっかり覚えて的確にできるように
- 平均点予想は55点前後
B問題
- 大問1から問題が長く、こちらも時間に余裕はない
- [1]生物:知識問題で、Bの中では比較的短時間で正解を出せたはず
- [2]世界遺産の問題:本文を読まずに解きはじめても大丈夫だった、山場は(6)の50〜100字記述、得点条件は表にある4つの評価基準の少なくとも1つをクリアしていること
- [3]化学:銅に関する燃焼問題、(4)〜(6)はややこしく難しかった、前半をしっかり取っておき後半は得意な受験生が差を付ける問題
- [4]地学:地層、(2)-①は簡単だがあとは難しかった
- 大問4つの中で苦手でないところでしっかり取れたかがB問題のカギ
- 時間はあったが読む量、考える量、答える量が多く平均点は低い予想
- 平均点予想は40〜45点
A問題
- 1問30〜40解かなければいけないので忙しい
- [1]地理:(4)プレートの境界がどこか、(6)日本三名園はしっかりおさえる
- [2]歴史:(3)/(6-2)細かい年号を覚えていないと順番付けられない、(8)明治・大正・昭和の年を覚えていないと答えられない、(9-1)戦後の代表的な出来事は年号と総理大臣をセットで覚える、(9-2)湾岸戦争とイラク戦争の区別が付いていない人が見受けられる
- [3]公民:答えやすかった内容、憲法関連の祝日
- 平均点予想は50点
B問題
- 何を書いたらいいのか思いつかなければ逆に時間が余ってしまう
- キーワードを入れていく問題はいけただろう
- (3-2)、(4)、(6)は書くのが難しい問題
- (10) ヤングケアラーが何かを一度YouTubeなど映像で見てみるのが良い
- 平均点予想は50点かやや切るくらい
感想
昨年の我が家は、第1回のみでこの第2回は受験しませんでした。
第1回と第2回で大きな違いはありませんが、6年上期のサピックスオープンはA問題/B問題に分かれていて午前午後の長丁場になる非常にタフな模試ですね。
B問題については算数でコメントされている通り、最難関校(特に男子)を意識した問題になっているようなので、志望する学校によって見直しに強弱を付けていいと思います。また、持ち偏差値の基準はあくまで6年下期の合格力判定サピックスオープンなので、ここまでの模試では成績よりも中身を見ることを重要視したいですね。
あと、コベツバと受験ドクターで若干コメントが違うので、両方を見て参考にした方が良さそうです。コベツバは算数が得点源の子に向けたコメントのようにも見えますし。
以上です。
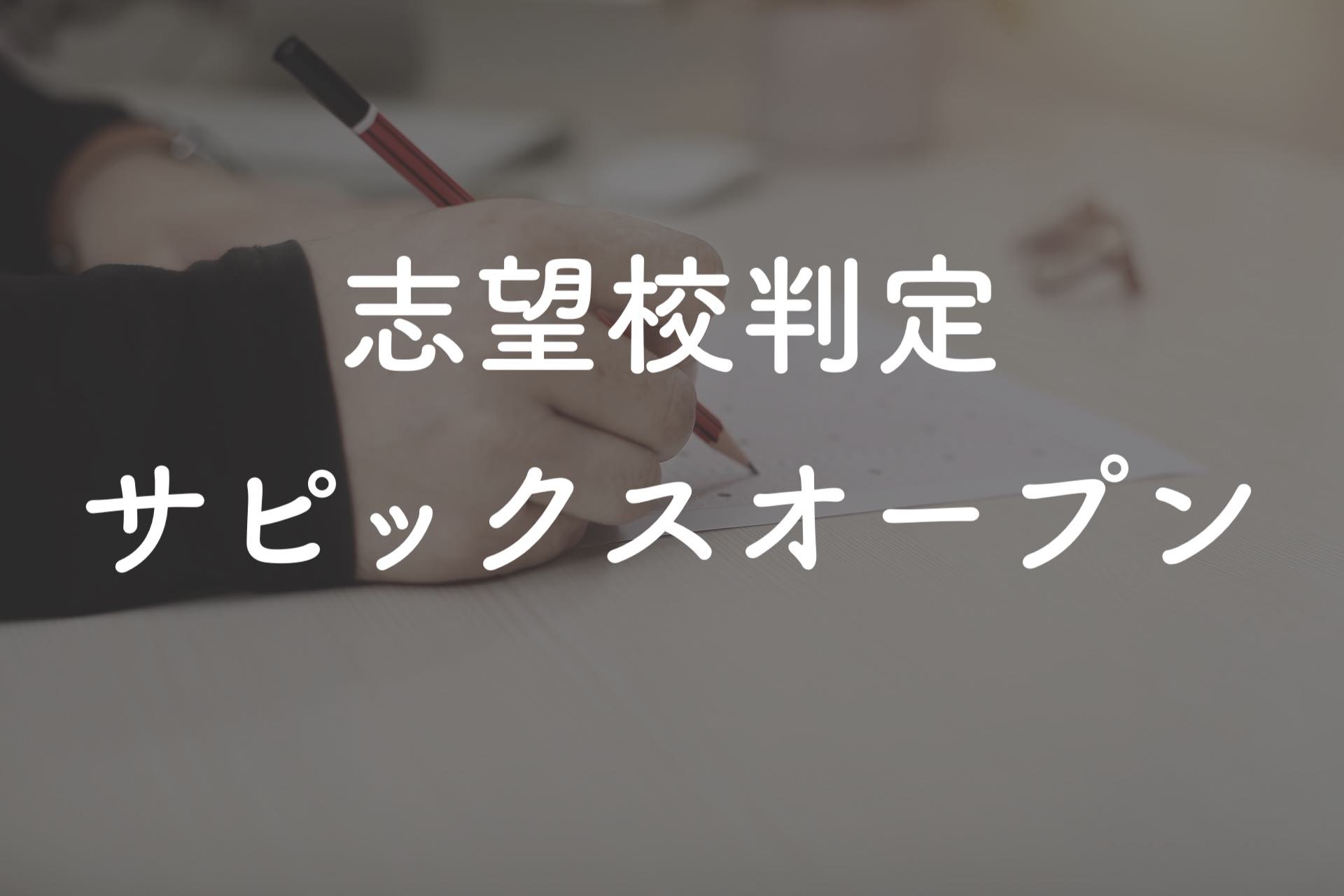
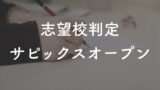














コメント