6年生の第2回合不合判定テストが昨日実施されました。おそらく今日時点で素点は出ていて見直しも進めている人も多いと思いますが、受験ドクターとコベツバから解説動画も出揃ったのでそれらを簡単にまとめます。
第2回合不合判定テストの基本情報や確認ポイントについては次の投稿も参考にしていただければと思います。
2022年 第2回合不合判定テスト
中学受験ドクターの解説
1時間を超える長い動画なので、もちろん全部を確認されるのがベストでしょうが、要点をまとめておくので見たいところをピンポイントで確認されるのも良いのではと思います。
国語
全体講評・平均点予想
- 全般的に読みやすい文章
- すごく簡単な問題と難しい問題が混在
- 平均点予想は女子85点前後、男子75~80点前後(本当は90くらいとってほしいが)
各問題の講評[1]
- 母親視点の物語で小学生には馴染みのない視点
- 物語の舞台設定は重要
- 「私」はなんの立場
- ジュリアという女の子の境遇
- 私自身がどのような境遇でどんな家族構成なのか
- 問1,2,5,7:身体記号を心情語に正しく置き換えていくことが重要
これらは本文に沿っていれば間違えない、もし間違えている場合は先に自分で解釈してしまっていて今後下がっていく可能性が高いので、表現に着目させる訓練が必要 - 問3:語彙問題は文脈から読めることもある
- 問5:母親の本音を言い換えたもの
- 問6(記述):部分点はもらわなければいけない問題だが満点解答は難しいかもしれない、何に母親が切なさを感じているか、親としての私の気持ちの2点が書けて満点
- 問8(記述):模範解答は抽象度が高いので、それよりもっと本文に沿った言葉でよい
各問題の講評[2]
- 松村圭一郎の文章は入試で本当によく出る(海城、開成、豊島岡、香蘭等)、エチオピアの話が多い
- 問1:脱文挿入問題(脱文挿入問題のヒントは接続後、指示語、キーワードにある、ここではキーワード)
- 問2と9は適切でないものを選ぶ問題
- 問1〜3は簡単
- 問4(記述):どうなった問題、四谷の記述問題は文章中から使うべき記述を見つけて書き換えればよいだけ、空欄はもったいない
- 問5:難しかった
- 問6:模試で出てくる言葉は入試頻出のものなので、模試で出てきたものをしっかり学習すると効率がよい
- 問9:ちゃんと読めていれば簡単、間違えていた場合は読解に力を入れて取り組むのがいい
- 問10:難しかった
- 問11:実力がついていれば簡単
各問題の講評[3][4]
- [3]問1は混乱した子が多かったかもしれない、問1以外はできないといけない問題
- [4]良く出る漢字、8問はできてほしい
理科
全体講評・平均点予想
- 物理が大問2つ、化学生物地学それぞれ大問1つずつの計5題
- 全体的に真新しいテーマは少なかったが、少しずつ捻られた問題や慣れていないと解きにくい問題があり、手間取った人が多かったかも
- 大問1,4は取りやすい、3も知っていれば取れる、2,5は難し目で得点はバラつきそう
- 平均点予想は男女とも47~52くらい
各大問の講評
- 化学:水溶液の分類
- 特徴をしっかりおさえおけば全問正解できる
- 生物:植物
- 前半は知識問題、導管と蒸散
- (3) ひねった計算問題、消去算として解く、時間をかけすぎない
- 物理:玉の運動
- 類題を解いたことがあるかどうかで解き時間が変わる
- 飛び出した落下はよく出題されるようになってきたので確認しておきたい
- 正答率や得点に差が出る大問だった
- 地学:太陽の動き
- ここはしっかり取りたい大問
- この大問が取れたかどうかで、時間配分がうまくいったかどうかを見る
- 最後はやや難しかった、思い切って飛ばすのもあり
- 物理:LED,手回し発電機
- LEDは一方通行というのは最低限知っておくべき知識
- 実験5はかなり難しめの問題、LEDの復習ということで時間をかけて解き直ししてほしい
社会
全体講評・平均点予想
- 歴史はまずまず、地理・公民は忘れているものも多そう
- 平均点予想は50点前後
各大問の講評
- 歴史
- 年表、解きやすかった
- 後醍醐天皇の漢字
- 地理:災害
- 近年出題が多い
- 気象庁がどこの省庁所属かは再確認
- 北緯35,45度、東経135,140度がどこを通るのかは即答できるように
- 環境・公害
- 持続可能、サステナブル、リデュース、リユース、マイクロプラスチックなどの言葉の意味と影響を説明できるように
- 歴史
- 5箇条の御誓文と五榜の掲示を混同しないように
- ポツダムがどこの国にある地名か(ポーツマスも)
- 財政・税
- 累進課税、税の逆進性などは確認したい
- 直接税と間接税の具体例
- 問8は図表をしっかり確認し復習してほしい
算数
全体講評・平均点予想
- 前回(第1回)よりだいぶ解きやすかった
- 平均点予想は男子は80を超えるくらい、女子は70〜75くらい(本当は90取ってほしいが)
各大問の講評
- 計算問題:計算のくふう、逆算の問題は答えを当てはめて確かめる習慣を
- 小問集合:6問全て素直な問題が並んだ
- 相当算:素直な問題で計算ミスさえしなければ解けた子が多いだろう
- 立体図形(円錐):円錐関連の公式をもう一度確認、(2)体積比が使えるか
- 周期の問題:(2)まではミスなく拾い切りたい、(3)一番処理量が少ないのは縦の長さ、横の長さをそれぞれまとめて計算する考え方
- やや難易度高めの小問集合:今回は比較的解きやすかった、(1)消去算は差を見るクセをつけてほしい、(2)偶数奇数の関係、もう一度確認しておきたい、(3)有名な図形問題、初めて見た人はしっかりおさえておいてほしい
- 平面図形:典型的な平面図形の比、(1)は6年生前半で平面図形と比をきちんとやってきたかが問われる問題、(2)色んな解答方針があるので、一番自分の方針で解けても、別の方針がないかどうかを考えてみる
- 速さ:2者間グラフ、普段のダイヤグラムと少し違う見方をしないといけないので、この時期だと最後まで解き切るのは難しかったかもしれない(入試直前には解けるよう仕上げる)
- 重量級の大問、ただ(1)は拾える(予習シリーズにも載っているタイプ)、(3)は時間制限的に厳しいが、数の性質の大問を出す
コベツバの動画解説(算数)
算数
- レベルAが6割、レベルCが1問、残り(4割弱)がレベルBという分類、第1回よりややレベルAの比重が高く得点しやすかったのではないか
- (合不合は)大問が9番まであるので1つ詰まると時間がなくなってしまうので時間配分が大事なテスト、前半でテンポ良く回答し軌道に乗っていけるかがポイント
- 出題範囲は幅広い、ただ図形の移動や大型(重め)の立体図形、ややこしい場合の数などはなかった
- 一般の入試で考えればオーソドックスに力を測る問題になっていた(立体図形や場合の数の難問を出さない入試という意味)
- 思考力要素の問題は5(3)、6(2)、9(3)くらいで、基本的には技術寄りの問題(四谷大塚の傾向通り)
コベツバ先生による各問題の所感と難易度分析についてはこちら。
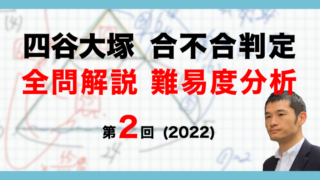
【バックナンバー】四谷大塚 第2回合不合判定テスト 算数動画解説・難易度分析(22年7月10日実施)
【2022年7月10日実施 四谷大塚 第2回合不合判定テスト】算数の全問解説動画と分析を配信。3年先まで予約で埋まった元プロ家庭教師が作成。「解説を読んでもわからない・もっと効率的な解き方で解きたい」方におすすめです。6年生にとって2回目の...
ドクター、コベツバともに、算数は第1回よりは得点しやすかったのではということでした。第1回はだいぶ平均点が低かったので(以下の投稿参照)、それよりは上がるのかもしれませんね。
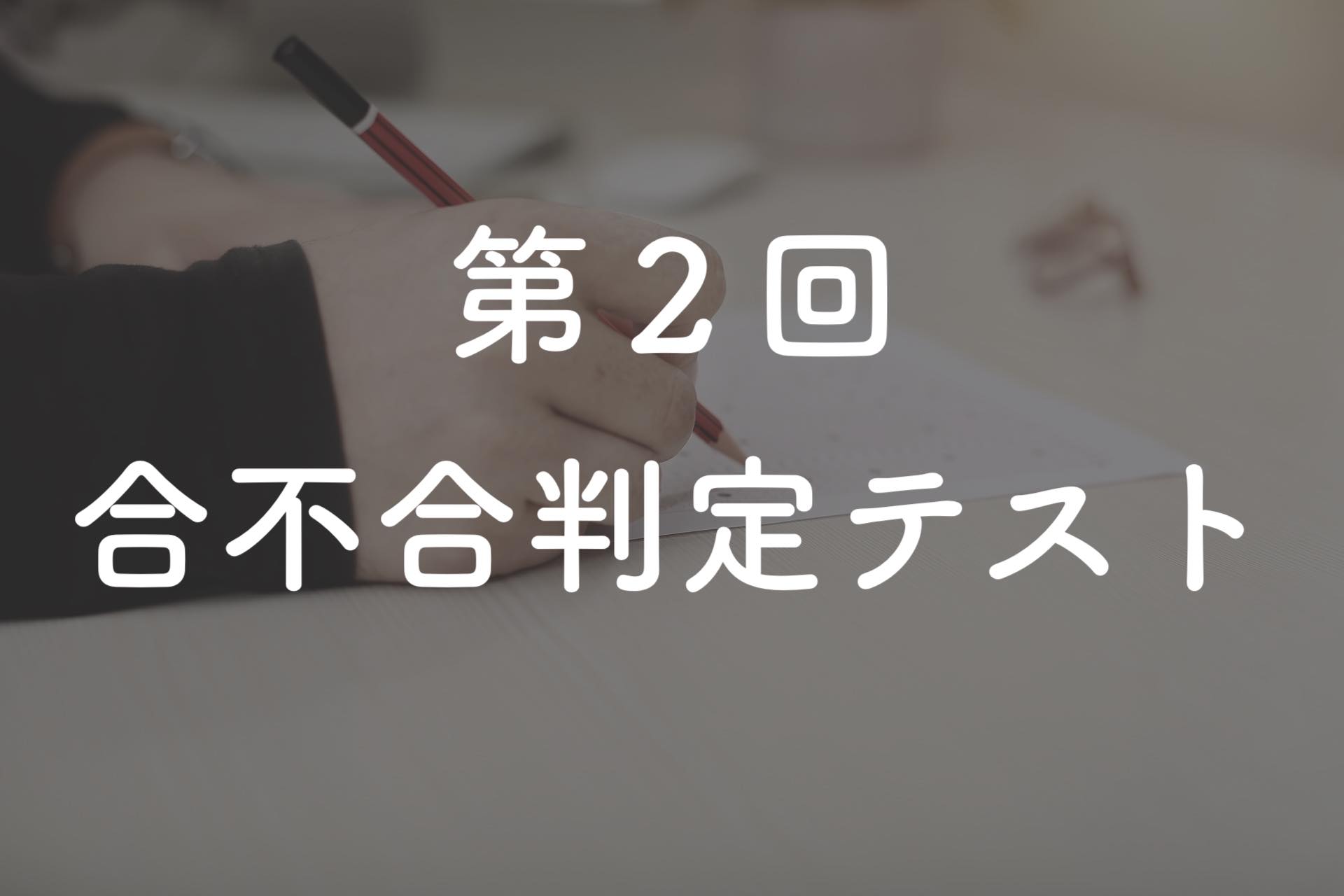
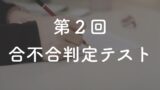
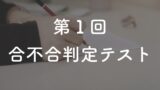














コメント