中学受験国語は、これを小学生に読ませるのかというような大人向けの題材が出題されることも多く、時間の割に文章量も多いので、多くの小学生にはハードルが高い科目だと感じます。
中学受験は算数が最重要とはよく言われますが、個人的に最も差がついているのは国語なんじゃないかと思ったりします。それは単純に点数差だけの話ではなく、できる子は家庭で大した勉強をしなくても勝手に点数を取ってくるので他の教科に時間を集中投下できる一方で、そうでない子(こちらが大多数の気がしますが)はいつまで経ってもできるようにはならず成績も安定しない感じになりやすいと思います。算数が飛び抜けてできるという一部の子を除けば、国語の成績がトータルの成績に影響しているケースが多いのではないでしょうか。
と思っていた中で、以下の記事を見つけました。ちょうど良い機会なので、この記事を題材に国語という科目について考えてみたいと思います。

国語塾を経営している方なので多分にポジショントークは入っていると思いますが、共感できる点と突っ込みたい点の両方があったので、その辺りから触れていきます。
超長文化する出題文
記事の最初で触れられているのが出題文の超長文化が進んでいるという話です。中学受験でも過去問を見れば一目瞭然で感じますが、ことは中学受験だけの話ではなく、大学受験でも高校受験でも同様の方向性になっているということです。大学入試共通テストの批評でもこれはよく耳にします。
そういう流れの中で、それに対応する塾のテストでも長文化が進んでいるので、答案を見ると後半が白紙とか、記述まで時間が取れなかったというご家庭も多いのではないかと思います。
ちなみに記事中にはこんな内容がありました。これには疑問を感じたというか、何を狙ってこういう書き方をしているんだろうというのを感じたので取り上げてみます。
例えば開成中学や麻布中学などの国語の問題文はほとんどの年で超長文ではありません。しかし、これらの学校の滑り止め校と言われる中学では、超長文が毎年のように出題されています。このように実際は学校ごとに問題文の長さは大幅に違うのです。
※2023年度の開成中学は50分で約1万2000字、すべて記述式なので設問の字数はとても少ない。他方、同校を受ける生徒が第2志望にする場合が多いある男子校は選択式問題が中心で、約1万5000字の問題文と約5000字の設問という量で出題されている。
まず1万2000字や1万5000字という数字が私の感覚とあまりに違うので、改めて2023年度の開成中学の入試問題で文字数カウントをしてみたのですが、以下の通りでした。
- 開成:9546字(論説文4250・文学文5296)
- ※ちなみにカウント方法は、PDFをAdobe Acrobatで文字認識したものをWordにコピペし、文章を修正した上でWordの文字数カウント機能で計測しています。さすがに全数を手で数えてはいませんが、手で1000文字くらいサンプリングしても数は同じなので信頼していいと思います。
過去を見ると開成は7000文字前後の年が多いので、まず2023年のこの9500文字というのは、開成としてはかなり分量の多い年だったと言えます。
そして「同校を受ける生徒が第2志望にする場合が多いある男子校は選択式問題が中心」ということで、この条件に当てはまり長文を出す男子校を考えると、可能性が高いのは海城か本郷です。この2校について調べた結果が以下の通りです。
- 海城①:7101字(論説文2901・文学文4200)
- 海城②:9487字(論説文4216・文学文5271)
- 本郷①:9499字(論説文4706・文学文4793)
- 本郷②:12418字(論説文5142・文学文7276)
海城は8000字前後が多く2023年は①が少なめで②が多め、本郷は①が少なめで②は多めでした。本郷②が多いですが、例年10000字前後なので、この年(回)がかなり多めだったという感じです。じゃあ開成の9500字と比べて多いのかと言われれば、本郷②は確かに多かったですがそれ以外は同等以下です。
ちなみに麻布こそ超長文を出題する学校として有名で、文学作品1題で8000文字を超える出題をしています。論説文がないのでトータルでの文字数はそこまで多くはないですが、1題の割に他校と同等の文字数ということで文章が非常に長く、何をもって超長文でないと言っているのかよくわかりません。
ということで、”開成や麻布では超長文がなく、これらの滑り止め校では超長文である”といった記載は、そもそも数字が大きく違うだけでなく、内容も間違いであると言わざるを得ないです。文字数はカウント方法の違いがあるのかもしれませんが、超長文を出すのは滑り止め校であるというのは事実とは言えないでしょう。「滑り止め校」という書き方といい、何らかの意図を持ってミスリードしようとしているように見えるのですが、何かあるんでしょうかね。
ついでなので、難関校に関して過去に調べた出題文の文字数を、多い方から一覧で挙げておきます。(ただし、機械認識した文字を修正してきっちり調べた学校とそうでない学校や、平均を取った年数の違いなど色々が混ざっているので、500字くらいの単位で丸めたざっくりの目安と思っていただければと思います)
| 学校名 | 文字数平均 |
|---|---|
| 浦和明の星 | 12,000字 |
| 栄東(東大特待) | 12,000字 |
| 浅野 | 10,500字 |
| 渋谷渋谷 | 10,500字 |
| 本郷 | 10,000字 |
| 桜蔭 | 9,000字 |
| 麻布 | 8,500字 |
| 聖光学院 | 8,000字 |
| 栄光学園 | 8,000字 |
| 駒場東邦 | 8,000字 |
| 海城 | 8,000字 |
| 攻玉社 | 8,000字 |
| 都市大付属 | 8,000字 |
| 女子学院 | 8,000字 |
| フェリス | 8,000字 |
| 洗足学園 | 8,000字 |
| 豊島岡 | 8,000字 |
| 開成 | 7,000字 |
| 早稲田 | 7,000字 |
| 芝 | 7,000字 |
| 渋谷幕張 | 7,000字 |
| 世田谷学園 | 6,000字 |
| 武蔵 | 5,500字 |
| 筑駒 | 4,500字 |
試験時間の違いもありますし、これを見ても、御三家が短く滑り止め校が超長文などという単純な図式でないというのはおわかりいただけるのではないでしょうか。
傍線部の前後だけを読む?
さて、気を取り直して先へすすみましょう。次にこんな内容があります。
ところが、塾でのテストの出題は、その多様性に対応することなく、一律に長文化の一途をたどっているようです。その状況のもと「傍線部までジャンプして、途中は読まず傍線部の前後だけをさっと読んで答えましょう」というような指導が、実際に進学塾では行われています。
さっきの話のあとなので、これも本当か?と疑いたくなる記載ですが、もし本当にこんな指導が行われているのだとすれば論外ですね。何のために国語を学習しているのか、単にテストで点が取れることだけを目的とした勉強なのだとすれば、そもそも受験勉強自体が害悪にも見えてきます。
こういった指導は私自身は聞いたことがないのでにわかには信じがたいのですが、色々想像してみると、例えば成績が下位のクラスで答案がほとんど空白になってしまうような子たちに対して、何も書けずに終わってしまうくらいならせめて問題の部分だけでも読んで何らか回答を書くようにしよう、という指導をするならまあありえるかなと思います。これがスタンダードになってしまうと怖いですが、一時的にどうしようもない現状を打破しようと悪あがきする中の一手であればアリじゃないかと思います。
上の記載では「実際に進学塾では行われています」と書かれているのみで、あたかもそれが進学塾の一般的な指導かのようにも受け取れますが、どんな状況でどのくらい行われているかも明確になっていないので、普通に行われているかどうかは定かではなく、これもまた勘違いを誘発する書き方だなと感じます。
何となく悪意を感じる書き方ではありますが、とりあえずこのやり方自体は国語の本質から外れているので、もし子供がそういう解き方をしているのであればやめさせるべきということへ次へ行きたいと思います。
長文を短時間で解くテクニック
で、著者の主張するテクニックがそのあとに紹介されています。これについては、実際に自分や息子で試していないので何も言えない(言うべきではない)と思いますが、まあ試してみることは悪くないということだけ書いておきます。
1. 文章の読む順番を変えることでの対応=最終場面チェック
論説文は最終段落に「筆者の言いたいこと」が書いてあるのが一般です。それゆえ、早く読む必要性が高い状況のもとでは、最終段落をまず読んで、「その文で筆者が何についてプラス、何についてマイナスと言っているか」を把握します。
入試の現場など物語文を急いで読む必要がある場合には、最終場面を先に読み結末がわかった状態で本文に当たったほうが、早く正確に物語を読解することができます。ただし、読書の楽しみは大幅に減りますので普段の読書ではお勧めしません。
2. 文章のテーマによる対応
論説的文章の書き手には、その文章を書くにあたって、前提としている「背景知識」があるはずです。ですから、その背景知識を前もって理解して記憶したうえで文章を読むことで、読むスピードや正確性が上がります。
物語の書き手には表現したいテーマがあり、それは登場人物の立場や人間関係によって規定される面があります。ですから、その登場人物の立場や人間関係を踏まえた「背景知識」を前もって理解して記憶しておくことで、物語文の理解の正確性やスピードを上げることができます。
3. 文法的な知識による対応
接続語の用法を理解して記憶していれば、接続語の前をA、接続語の後ろをBとした場合「A→接続語」と読んできた段階で、Bの内容はある程度推測できるものです。
(略)
ですから、文章を精密に読む場合には「省略された主語」を補う意識が必要です。
これは批評ではなくあくまで個人の感想ですが、1と3の考え方は個人的にはあまり好きではありません。1番は最後の段落を読んだだけで全体の内容を理解できるのかという疑問があるし(実際にやってみましたが唐突感があって意外と把握が難しい)、3番は文法に意識を集中していると内容が頭に入ってこないんじゃないかと感じます。
接続語を意識しなさいといった文法に関する話は国語の参考書にもあるし、模試の解説動画でもよく聞くので、国語の受験指導としては一般的かなとは思います。ただ、いちいち「つまり」が来たから言い換えだなとか、「しかし」が来たから逆説だなどと考えていたら、頭のリソースがそっちに持っていかれて、内容把握するために使う頭のスペースがなくなってしまわないかと思います。まあそういう国語の基礎がない段階の子が訓練のためにやるというのはありかもしれませんが、実際にテスト問題を解く時点では、その辺は当たり前に身に付いていないと短時間で解くどころの話ではないと思います。
国語はテクニックで解くものではないのでは
ということで、(書こうと思った当初の意図に反して)だいぶ記事をこき下ろしてしまった感がありますが、この中でひとつ共感できたのは「背景知識を持った上で読む」というところです。というか、スピード感を持って読むにはこれしかないんじゃないかと思っています。
文章を読んでいく中で「あー、この話ね」と先の展開がある程度予想できると、予想と合っていれば結局それを裏付けるような話が展開されていくことになって理解が深まるし、外れていた場合も、予想をガイドとしてそこと何が違うのかという観点で読んでいくことができるようになります。
ただここで私が考える”背景知識”は、著者の書かれているような単純な項目のパターンではありません。例えば「A 二元論スペシャル①(理性と感情の対比)」「B 二元論スペシャル②(自己主張の文化と、妥協と協調の文化の対比)」とか言われても、何のこっちゃというか、大人でさえパッと頭の中にイメージできないと思います。物語文の「A 成長の物語」「B 愛の物語(親の愛)」とかならまあ何となくイメージできそうなんでこっちは使えそうですが、それでもやっぱり粗いと思います。
じゃあその背景知識は何か・どこで身に付けるかということですが、結局似たような文章を過去に読んで考えたことがあるかということに尽きると考えています。受験勉強をやっていく中でたくさんの文章に触れ、解いていく中で、これらの知識が子供の頭の中に蓄積されていきます。分かりやすいところで例を出すと、SDGsに関連した文章であれば、温暖化に触れられていて地球環境を守るために我々が取り組むべきこと、みたいなお決まりのパターンがあるので、読みながら先の展開が想像がつくはずです。物語文でも、中学受験ではあまり突飛な内容は出されないので、基本的には主人公が何かの出来事を経験して成長するとか、親の愛に気付くとかいうパターンが蓄積されていけば、自然と予測できるようになるでしょう。
ということで結局、国語力はテクニックでどうこうするものではなく、読んだ文章量に比例して上がっていくものであると私は捉えています。
国語力は子供の成長度合いで決まるとか、受験直前に突然伸びたみたいな話をネット界隈でも目にします(我が家もその例にもれず小6の秋に覚醒しました)。それだとじゃあ精神的な成長に賭けるしかないのかという話ですが、一方で受験勉強もしていない子が急に難関校の問題が解けるようになるわけでもないので、要するに日々の勉強で蓄積してきたものが、どこかの閾値を超えたときに繋がって解像度が上がり、その結果が表に現れたものだと捉えるのが個人的には一番しっくりきます。
最初から国語の成績が良い子というのは、幼い頃から読書をして多くの文章に触れ蓄積したものが多いとか、日々の会話や身の回りのものから得る情報量が多いなど、いずれにしてもこれまでの経験からくる背景知識が多く理解力が高いということではないかと思います。
そういう意味で、国語力を上げるということに近道はなく、いつか花開く日を信じて日々問題に取り組むしかないというのがここでの結論になります。(なんてことを言うと元も子もないですが)
まあ直前期の6年生だとちょっと話が違ってきて、本番まで時間もないので、記事の内容を試したり悪あがきをするのはアリだと思います。我が家も解き方を変えてみたり(参考:国語の解き方の流派)試行錯誤はしました。ただ5年生(6年生前半くらい)までは、コツコツ努力を積み上げて焦らずに待つというのが王道なんじゃないかと思います。
国語の授業ってどうなん?
以上が記事の内容をベースにした話です。基本これで終わりなのですが、最後に、どうしても腑に落ちない国語の授業について少しだけ触れておきます。
塾の国語授業ってどれだけ効果があるんだろう?というのは兄が受験勉強していた時に感じていたことでした。兄は四谷大塚の進学くらぶで動画授業を受けていたのですが、当初は動画も見ていたものの、途中から時間がもったいなくなって見るのをやめました。(その後の取り組みについて、興味がある方はこちら(参考:国語の勉強について)をご覧いただければと思います)
問題を解いて、その内容と解答について解説を受けるという集団塾の授業スタイルは、個人的には無駄が多いというか、その授業を聞いてできるようになる気がしません。その時間を文章読解に回して、読む量を増やした方が効果的じゃないのかなと思ってしまいます。
で先日、そういえば私立中学校の授業ってどうなっているんだろう?とふと思い立ち、兄に聞いてみました。そこで初めて知ったのですが、どうやら我々の時代とは違った授業スタイルらしいということでした。検定教科書を使わずに独自プリントというのは国語に限らず私立中学の基本スタイルみたいですが、そこで配られた課題文を読んだ上で、チームごとに話し合ってまとめて発表するというのがイマドキのやり方のようです。これは集団授業ならではですし、国語力云々は一旦置いておいても、他者と意見をまとめたりプレゼンしたりというのは将来的に役立つので、そういう経験が日頃からできるのはとても良いと感じました。
集団授業=自分の頃と変わらない受け身の授業だと勝手に先入観を持っていましたが、必ずしもそうではなかったようです。以前、麹町中学で学校改革した工藤校長の動画を紹介し(参考:一斉授業の廃止に動いているらしい横浜創英)、こういうのをキッカケに教育環境が変わっていってほしいと思っていましたが、派手に注目を集める学校改革だけでなくても、地味ながら着実に変わっている部分も実は存在しているんだというのはひとつの発見でした。この手の話はあまり表に出てこないので情報収集が難しいのが難点ですが。
そういえば1年前くらいに取り上げた、伝統校vs.新興校というおおたとしまささんの記事でも、こんな内容があったなというのを思い出しました。
だいぶ話が逸れていってしまったので話を元に戻しますが、塾の方は(国語に限らず)昔からのスタイルを貫いているところが多いように感じます。日能研の最上位クラスで討論形式の授業があるという噂を聞いたことはありますが、それがメジャーになるかというとそういう感じはしません。
私立校の新しい授業スタイルを手に入れるために、昔ながらのスタイルで勉強するというのもなかなか皮肉が効いていますが、そろそろ新しい方向性があってもいいんじゃないですかね。コロナ禍を経て何かが変わるようにも見えましたが、大手塾を見る限りは元に戻ったという印象の方が強いです。
我が家の話で言うと、兄の中学受験が終わって1年半経ち、弟の本格始動まであと1年半というところまできて、そろそろどういう方向性でいくかを考えたいところです。現時点ではあまり選択肢が変わっていない感じを受けていて、おかげでノウハウが陳腐化しなくていい面もありますが、せっかくなんで何かもっと違ういいやり方があると面白いなと思っています。
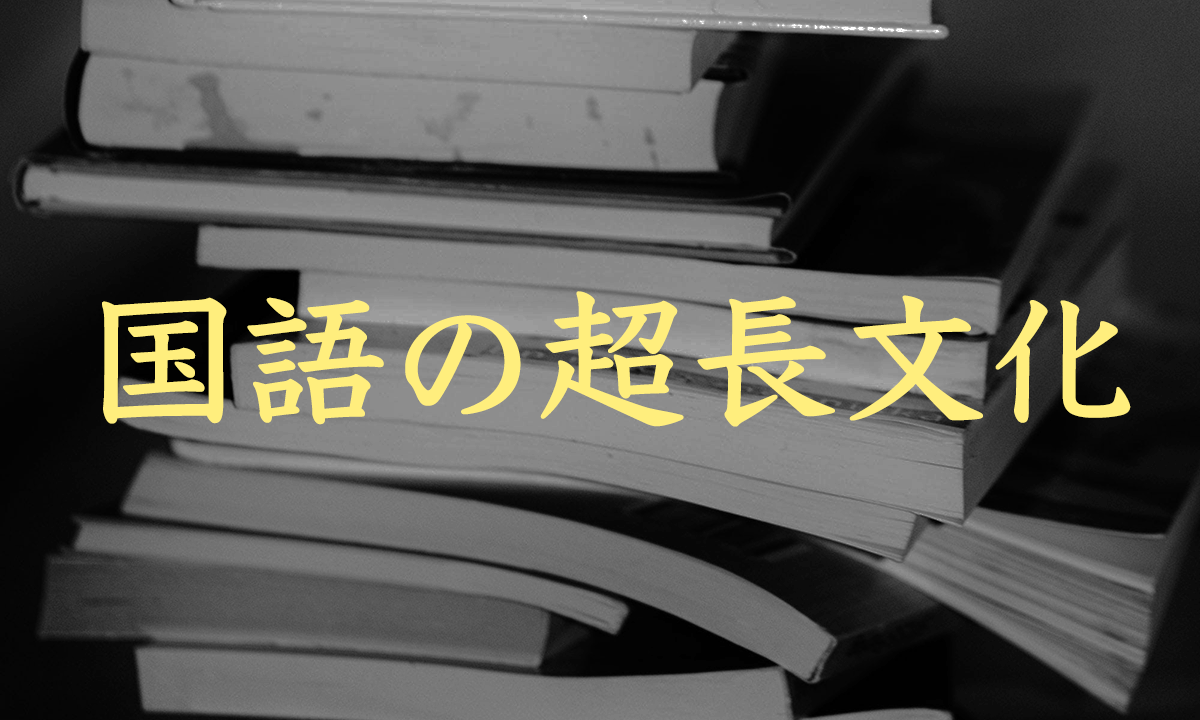













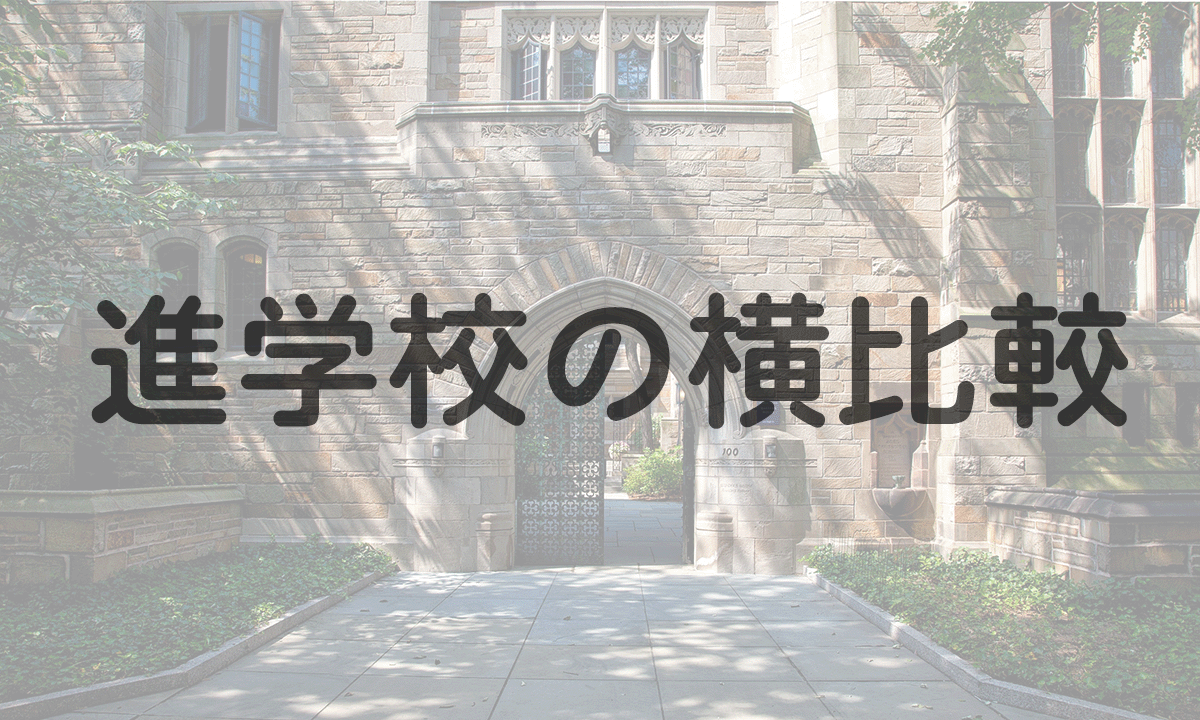
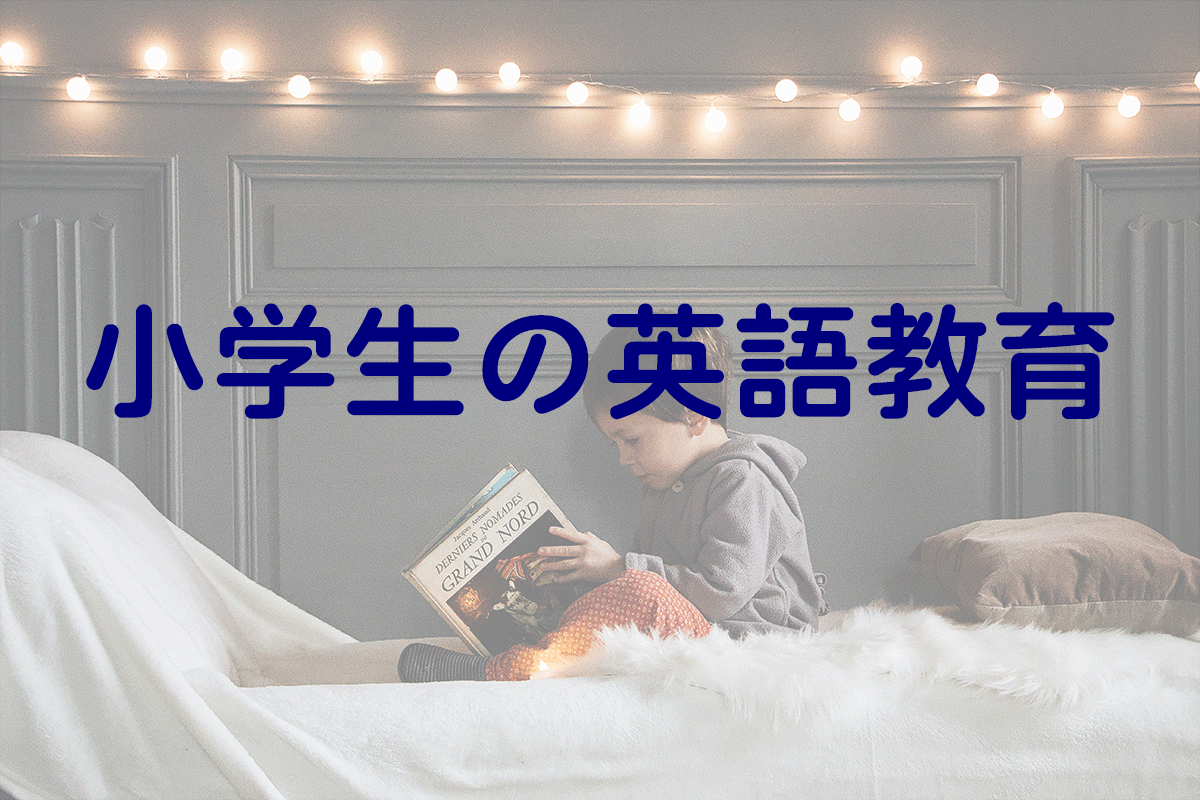
コメント