3年ぶりに気兼ねせずに出掛けることのできたであろうゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。我が家もわずかながら帰省したりしていましたが、そこで改めて感じたこと・考えたことがあったので記しておきます。
本当にあったコワイ話
この時期に田舎に行くと、田んぼに水が入ってしろかきをしていたり、早いところでは田植えを始めたりしていて、ちょうど田んぼの景色が変わるタイミングに出会えます。
ここで思い出したのが、上の子の受験勉強サポートを本格的に始めて気付いたときの話です。時期は定かではありませんが、予習シリーズの4年下にある「米づくり」の単元を見たときの話だったと思います。

お米ってどうやって作られてるか知ってる?

え、わかんない。

田舎に行ったときに田んぼあったでしょ?

・・・(田んぼ?)

ほら、家の近くにあったじゃん、緑の葉っぱがいっぱいあって、、、

・・・。

えーと、、家を出て右にちょっと行ったとこの角にさ、葉っぱがシュッシュッと出ててさ、、うんぬんかんぬん、、、
米作りどころか、田んぼがどういうものかというところからスタートしないと話が通じないということが発覚しました。
もっと衝撃的だったのはこちら。

北ってどっち?

え?こっち?
あれ?あっち?
・・・わかんない。

...じゃあさ、太陽が昇ってくるのはどっち?

え、、、わかんない。

えっと、じゃあ、、、太陽が沈む方は?
外に遊びに行ったときどっちに太陽ある?

・・・わかんない。

ぐぬぬ、、、
「お天道様が西から昇る」という例えがありますが、そんな言葉の前にその前提さえもよくわかっていないという。
考えてみれば、ビルに囲まれ夜も明るい都会に暮らしていれば、太陽を意識することもなければ方角を考える必要もない、太陽がいつどこへ沈んだのかもよくわからない、という状況になっているのも当然といえば当然でした。
田舎育ちの自分には、通学路の田んぼの景色は季節によって当然のように変わっていくし、ましてや太陽がどっちから昇ってどこへ沈むのか、夏は日が長く冬は短いこと、季節によって太陽の位置も違うなどといったことは、別にあえて授業で習わなくても毎日生活していれば当たり前のように体感していたことでした。
それが、我が子には当たり前ではなかった。田舎に行ったときに見た田んぼの景色はただの背景で、太陽は昼には上の方にある、という程度の認識しか持っていなかったということでした。そしてこれが小1・2とかではなく、中学受験勉強なるものをスタートしたあとの4年生での話です。
コワイですね。
こんな程度の認識で授業に出て、やれシロカキだタウエだなどと言われても、それは単なる記号の羅列でしかなく、頭の中に何のイメージも持たないまま単語を丸暗記していく勉強になるでしょう。そんな状態では定着するとかしないとかいうより、苦行でしかありませんね。
ここから得た教訓はこんな感じです。
自分の当たり前は子供の当たり前ではないと認識すること
都会暮らしと引き換えに失ったものは、意識して与えなければいけない
これに気付いて以降は、実験や体験のできるものは可能な限り参加したり、NHK for Schoolなどビジュアルにイメージできるようなものを選んで与えるようにしていました。
個人的には親の方がここに気付けただけでも中学受験を始めた価値はあったと思っていますが、むしろ受験勉強を始める前の低学年こそ、いざ勉強を始めたあとにイメージできるようなことをやっておくべきだろうと今は思います。
理科・社会こそ先取りが有効かもしれない
若干煽り気味のタイトルではありますが、理科・社会は座学に入る前に前提知識を入れておくことが重要、という意味で先取りした方がいいんじゃないかという話です。
どこぞの難問題集を買って解こうとかそういう話ではなく、日本地図パズルで都道府県と県庁所在地を覚えておくとか、路線図で新幹線がどこを走っているのか見ておくとか、家庭菜園で野菜を育ててみるとか、プラネタリウムで星を見るとか、まずはそんなところの話からです。そんなんとっくにやってるわ!という方も多いと思いますが、これをやってるかやっていないかで結構大きな差が出るだろうなと思います。それは、理科・社会の中学受験テキストを見てみるとわかります。
例えば予習シリーズ・4年上の社会のカリキュラムの一部を抜粋してみます。
| 第4回 | 都道府県と地方(1) |
| 第6回 | 都道府県と地方(2) |
| 第7回 | 地図の見方(1) |
| 第8回 | 地図の見方(2) |
| 第9回 | 一年中あたたかい地方のくらし |
これだけ羅列しても何のことやらという感じですが、具体的に内容を書くとこんな感じです。
| 第4回 | 都道府県と地方(1) | 北海道〜中部地方までの都道府県・県庁所在地を覚える |
| 第6回 | 都道府県と地方(2) | 近畿〜九州・沖縄までの都道府県・県庁所在地を覚える |
| 第7回 | 地図の見方(1) | 地図記号を覚える |
| 第8回 | 地図の見方(2) | 等高線や縮尺を理解して地形図が読めるようにする |
| 第9回 | 一年中あたたかい地方のくらし | 沖縄についての深掘り |
つまり都道府県と県庁所在地は第4回と第6回の2週間で47都道府県分すべて覚えなければいけない、ということです。すぐ翌週からは地図記号も同様に2週間で全てマスターし、第9回からは各地方の細かい話に入っていくので、基本的にはその週の単元はその週の中で消化していかなければなりません。こんな感じで毎週毎週覚えなければいけないものの波が容赦なく襲ってきて、週テストや組分けテストで嫌というほどその結果をアピールしてくるのが中学受験塾のカリキュラムなので、ちょっと今回は大変だわなどと躓いているヒマはありません。
逆の視点で見ると、都道府県名を覚えてしまっている子は第4回・第6回と楽勝で乗り切り、他の科目に時間を割いたり、社会という科目に対して自信を持つことができるかもしれないということになります。
分かりやすい例として都道府県名を挙げましたが、これは別に特殊な単元を取り上げた話ではなく、全てがこんな感じで進んでいくので、何の準備もなしに突入してしまうとかなり苦しい戦いを強いられるというのが実際のところだと思います。ちょっとした準備の差のような気がしますが、こうした積み重ねが結果的に成績・偏差値の差となって現れてくると考えています。
とは言っても、既に4年生まで受験勉強が前倒しされている中で、さらに低学年にまで前倒して勉強漬けにするというのはちょっとやり過ぎですよね。少なくとも低学年の間は、楽しんでいる間に自然に覚えているという方向を目指したいです。
具体的な手段はまだ模索中ですが、ひとつ自分がやろうかなと思っているのは、3年生の段階で4年生の予習シリーズを入手して(というかもう入手していますが、、、)、親が予習しておくということですね。ひととおり目を通し、そこで習う予定の内容を、オモチャでもマンガでもアプリでも動画でも旅行でも、何らかの別の手段でインプットしておくというのを考えたいかなと思っています。
あくまでも強いる勉強ではなく、知ることが楽しいと思えるようなやり方を模索したい、そうして学ぶことが楽しいと思えるようになってくれると良いなと思いますね。少なくとも理科・社会は、やり方によって大好きにも大嫌いにもなる、そういう科目じゃないかと思っています。
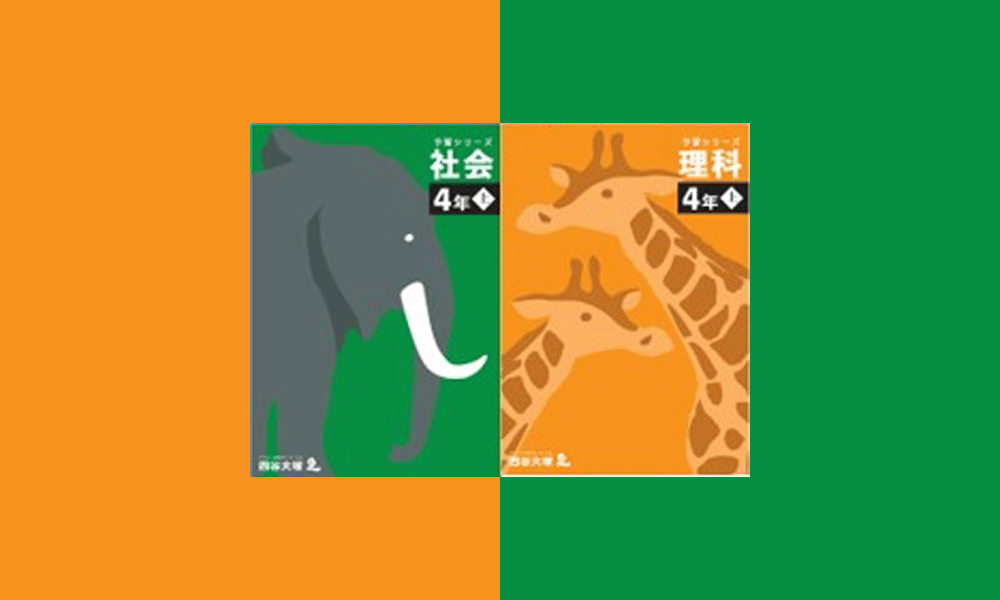














コメント